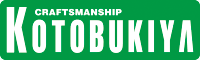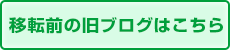-
フォルムアームズ カラーリングコンテスト 結果発表 第2弾!!
皆様こんにちは!フォルムアームズチームです! ご応募受付しておりました、 「 フォルムアームズ カラーリングコンテスト Round 2 ~SHO-RO-KI GRAND RISER~ 」! 本ブログにて、審査結果の 発表 となります! 審査と発表にあたって ・作品審査はデザイナーであるseraさん、 フォルムアームズチームメンバー によって行っております。 ・掲載は投稿日順です。 ・以後、作品名をクリックすると作品投稿のツイートにジャンプします。 (Twitterのアカウント設定を非公開に設定されているアカウントへは、このページよりジャンプすることはできませんのでご了承ください) 優秀賞 ■投稿者名 ミスティ 様 ■作品名 ザンファロン フォルムアームズチームコメント : 扱いが難しそうな各色ですが、まとまって見えるのがすごい!自分ではとても思いつかない、可能性を広げてくれる作品です! ■投稿者名 まさ(GPB) 様 ■作品名 ノーブルライザー フォルムアームズチームコメント : ホワイトをベースにした美しいカラーリングですね!差し色のクリアーパーツも上品なカラーをチョイスされてセンスを感じます!投稿者のコメントの通り使用パーツもハイグレードなものを使っているのも説得力あります! ■投稿者名 けん1/1 様 ■作品名 GR-タイプロイヤルガード フォルムアームズチームコメント : ザ・高貴!膝のディテールもエングレーブのように見えてとてもカッコいいですね。水色の差し色はもちろん、各部の紺色がとてもいいなぁ・・・!と思いました。 デザイナー賞 ■投稿者名 るまごんだ🦁ライブラ 様 ■作品名 サテライト・ライザー sera氏コメント: コメントにもあるように量産機感がある良いカラーですね。元々のヒーロー然としたカラーとは逆の印象にも魅力を感じました! そして最優秀賞は・・・! 最優秀賞 ■投稿者名 歩く鷹 様 ■作品名 マグナエンペライザー フォルムアームズチームコメント : 通常の赤いグランドライザーに対して、黒をベースとした機体。まるで敵対する事が決まってそうな兄弟機のようですね!デザインだけでもドラマを感じさせるという、ロボットアニメの定番をもイメージした素晴らしいカラーリングでした! 入賞されたみなさま、おめでとうございます!! そしてもちろん!今回も本コンテストはこれで終わりではございません。 最優秀賞作品を投稿いただいた歩く鷹様には、 「翔龍機 グランドライザー」 のパッケージイラストを入賞作品のカラーリングにした スペシャルパッケージ をお送りいたします!! そしてそのスペシャルパッケージ画像がこちら! 今回、パッケージイラストを担当いただいた井口佑様より本コンテストのために作成いただきました。 改めまして本当にありがとうございました! 以上となります! 今回も悩みに悩みぬいた審査となりました。皆さん本当にセンスがすごい! カラーリングはもちろん設定に凝っている作品も多く、数々のストーリーを思い描くことができ一同とても楽しかったです! あらためまして・・・ 本コンテストへご応募いただいた皆様、 本当にありがとうございました! ■受賞者へのみなさまへ 賞品発送に伴いX内にて、フレームアームズ・フォルムアームズ公式( @faman_type001)アカウントよりダイレクトメッセージをお送りさせていただきます。 ※翌日 4/1(火)にご連絡予定です メッセージの内容を確認のうえ、ご対応のほど何卒よろしくお願いいたします。 © KOTOBUKIYA

-
フォルムアームズ第二弾「翔龍機 グランドライザー」発売!
コトブキヤショップ限定 フォルムアームズ第二弾 「 翔龍機 グランドライザー 」 本日より発売です! ついに2体並びましたフォルムアームズ! 「 より手軽に、より手に取りやすく 」がコンセプトの本シリーズですが、これでより楽しめるのではないでしょうか・・・! さて、そんな「翔龍機 グランドライザー」ですが、 デザイナーsera氏 による作例も公開しております。 どんな風にミキシングすればいいのか・・・ぜひぜひご参考ください! ※画像クリックでそれぞれの解説ページへジャンプできます。 ちょっとカッコよすぎるな・・・ レイルヴァースよりマッシブな印象の本機ですが、可動域はこんな感じ。 1枚目なんかレイルヴァースより大きく曲がっちゃってます。 肘、膝関節もおなじみ3ミリ軸となっておりますので拡張性もばっちりでございます。 ということでフォルムアームズ第二弾「 翔龍機 グランドライザー 」のご紹介でした! ぜひぜひ、お手に取って遊んでいただけると嬉しいです!

-
フォルムアームズ カラーリングコンテスト 結果発表!!
皆様こんにちは!フォルムアームズチームです! ご応募受付しておりました、 「フォルムアームズ カラーリングコンテスト Round 1 ~RAIL VIRTH V.F.A~」! 本ブログにて、いよいよ審査結果の 発表 となります! 審査と発表にあたって ・作品審査はデザイナーであるseraさん、 フォルムアームズチームメンバー によって行っております。 ・掲載は投稿日順です。 ・以後、作品名をクリックすると作品投稿のツイートにジャンプします。 (Twitterのアカウント設定を非公開に設定されているアカウントへは、このページよりジャンプすることはできませんのでご了承ください) 優秀賞 ■投稿者名 あおあき 様 ■作品名 RV-B01 フォルムアームズチームコメント : まず設定が熱い!物語への想像が膨らみますね。対となるカラーをどこで区切るか・・・という難しいポイントもしっかりおさえたカッコいい作品です! ■投稿者名 歩く鷹 様 ■作品名 黒桜 フォルムアームズチームコメント : 暗めのベース色に浮かび上がる桜の花びら。美しいながらも遭遇してはいけない死神のようなイメージを感じました。投稿者様の言う通り刀や薙刀などの武器を持たせたら、多分刀身から赤や紫の炎がメラメラと揺らめいているはず! ■投稿者名 ワヒロ 様 ■作品名 レイルヴァース量産試作機 フォルムアームズチームコメント : どんな色にも染まるホワイトをベース色にする事でプロトタイプを表現しつつ、控えめのマーキングや差し色のパープルがとてもオシャレ! 地味になりがちな"量産機"ながらオシャレに演出できるセンスが光っておりますね! デザイナー賞 ■投稿者名 はくたし 様 ■作品名 レイルヴァース 野戦機 sera氏コメント: シンプルに良い色選びだなと感じました。カラバリ商品という視点で見ても魅力的です! 最優秀賞発表...の前に!特別枠作品についてご紹介! ■投稿者名 -moino- 様 ■作品名 mummy of god anubis 【マミー オブ ゴッド アヌビス】 ※特別枠について 当作品は匿名での審査の次点で 賞の候補として挙げられたのですが、 「陸上自衛隊07式戦車 なっちん」プラモデルシリーズで コトブキヤとして お世話になっております -moino- 様の作品でございました。 「陸上自衛隊07式戦車 なっちん」プラモデルシリーズでもお世話になっておりコトブキヤプラモデルシリーズとして身近なイラストレーター様であったため、 今回は特別枠として別枠を設けさせていただきました次第です。 -moino-様、 この度はご参加いただきありがとうございます! フォルムアームズチームコメント : インパクト特大の作品!上半身の模様はもちろん、ひざ下のマーキングも非常にクール。大量のマステを用意して再現塗装もしてみたい! そして最優秀賞は・・・! 最優秀賞 ■投稿者名 あまとき 様 ■作品名 レイルヴァースTypeA フォルムアームズチームコメント : コメントにあるように主人公機でありながら量産機にも見えるカラーリングですね!グレーを基調として量産機っぽさを演出しつつ、ホワイト、ブラック、イエローを配色して主人公機にも見えるギリギリの塩梅が素晴らしいと思います! 入賞されたみなさま、おめでとうございます!! さらにさらに、本コンテストはこれで終わりではございません。 そう!最優秀賞作品を投稿いただいたあまとき様には、 「レイルヴァース V.F.A」 のパッケージイラストを入賞作品のカラーリングにした スペシャルパッケージ をお送りいたします!! そしてそのスペシャルパッケージ画像がこちら! 今回、パッケージイラストを担当いただいた雪城 千冬様より本コンテストのために作成いただきました。 雪城様、改めましてありがとうございました! 以上となります! 審査の方は我々も非常に悩むこととなりまして、熱い議論が繰り広げられる事となりました。 我々のあっと驚くような、作品の数々・・・本当に カッコいいものばかり でした! あらためまして・・・ 本コンテストへご応募いただいた皆様、 本当にありがとうございました! ■受賞者へのみなさまへ 賞品発送に伴いX内にて、フレームアームズ・フォルムアームズ公式( @faman_type001)アカウントよりダイレクトメッセージをお送りさせていただきます。 ※翌日 3/19(水)にご連絡予定です メッセージの内容を確認のうえ、ご対応のほど何卒よろしくお願いいたします。 © KOTOBUKIYA

-
フォルムアームズ第一弾「レイルヴァース V.F.A.」ついに発売!
コトブキヤショップ限定 フォルムアームズ第一弾 「レイルヴァース V.F.A.」 がついに 本日より発売 です! コトブキヤのフレームアームズの魂を継承する新しいシリーズの第一弾キットになります。 詳しい仕様はこちらの記事を! フォルムアームズ第一弾「レイルヴァース V.F.A.」ご予約開始! 成型色・可動範囲・フレームアームズとの互換性 などフォルムアームズの全てが記載されております! ■コンセプトについて 第一弾発売であらためてですが、シリーズの コンセプトは「より手軽に、より手に取りやすく」 になります! まずは購入していただくハードルを下げるために、 できるだけですが 価格を抑えました (そのためにコトブキヤショップ限定品にはなりましたが) このコンセプトは価格面だけでは無く 「構造・組み換え」 に関しても時間の無い現代人に向け 手軽に楽しめるような仕様 を目指しました! ただもちろんこの 作例写真のように フレームアームズの経験も踏まえて カスタマイズの可能性は無限大! 、 より深く楽しめる内容 なっております(写真はグランドライザーをベースにしております) ■デザイナーからのコメント ここで デザイナーのsera氏からコメント をいただきました! ■デザインについて 初めはスリムでシンプルなロボが作りたいっていうふわっとしたイメージでした。 そこからメリハリも欲しいと思い、女性アスリートをイメージしたシルエットになっていきました。 腰リアアーマーと太腿のラインなんかはかなりアスリート感あると思ってます! 各部位も細ければ細いほど良い、と思いながら構築していましたがやりすぎるとただの骨になってしまうので気を使いましたね。腰や二の腕あたりはデザイン的にもかなりギリギリのラインだと思っています。 頭部は良くある形、に見せかけて結構独特な形をしています。 後頭部なんかはヘルメット感が出過ぎないようにラインを取っていたり、トサカや頬当ても、実はそれぞれポニーテールやもみあげ要素の名残だったりします(パーツ干渉の関係で現状の形に変化したわけですね) 私はフレームアームズから本格的にコトブキヤプラモデルを触り始めたこともあり、思い入れの強さからかなり構造やバランスを参考にしています。 フォルムアームズは企画当初からフレームアームズとの連携を考えられていますが、実はその前段階のガレージキット時点でその要素は存在していたんですね。 あとはすごく地味な要素なんですが、股下のベース接続穴がかなり後ろの方に用意してあるのも特徴だったりします。 こうすることでベースの接続部を目立たなくしたり、アクションの邪魔になりにくいといったメリットがあるんですね。 名前について・・・・ レイルヴァースの名前の由来は「Rail Birth(レールの誕生)」を意訳して「道を作る者」からきています これはガレージキット販売するときにその道しるべになってほしいっていう願いが込められております。 sera氏コメント有難うございます! ■M.S.Gも同時発売! sera氏デザインのM.S.G4種もまとめて本日同時発売です! 当たり前ですがバッチリ似合いますね!!レイルヴァースに付属武器はございませんので、もしお手持ちの武器が無ければ、こちらもお勧めです! 今回はここまでになります! コトブキヤショップ限定フォルムアームズ 「レイルヴァース V.F.A.」 をよろしくお願いいたします。 更に3月はシリーズ第2弾の 翔龍機 グランドライザー も控えておりますよー! 是非宜しくお願いいたします! © KOTOBUKIYA

-
フォルムアームズ「翔龍機 グランドライザー」作例紹介第三弾
こんにちは、seraです グランドライザーの作例制作、第三弾となります! 最後となる今回は「自分の中のカッコいいを追求する!」というテーマで作例をご紹介していきます ◆作例3:蒼龍機 グランドラウザー 3体目は1,2体目とは少し異なり、私がグランドライザーを純粋にカッコよくアップデートするとどうなるかというコンセプトで制作しています 言うならば 「グランドライザーコンペ」というコンペがあったとして、入賞を目指すならどんな構成にするか 、という事ですね なので今回はミキシングのお話はもとより、私なりのコンペに挑むときのやり方なんかにも触れていきたいと思います 使用パーツは 過去のフレームアームズのコンテストでのレギュレーションに準拠するかたちで 「翔龍機 グランドライザー」の他に今回はヘキサギアとM.S.Gをミキシング また仕上げに ハイキューパーツ様の水転写式デカール を使用しています 肩と脚の追加装備はポジションを変更して攻撃形態へと変形します たった二か所の変形ですが、脚部と肩というシルエットを構成するうえで重要な部位なのでかなり印象が変わりますね 脚部はパッと見で「変形するな!」と感じ取れた部分かと思いますが、肩の方は感じ取れなかったかもしれません コンペって最初のインパクトが結構重要だと思ってて、単純に「カッコいい!」と思ってもらうことはもちろん、「この部分は変形するな」という予想通りと「そこが変形!?」という予想を裏切る要素の複数のインパクトを感じてもらう狙いですね ここでは装備の変形にフォーカスしてますが、パーツの使い方や塗装方法なんかでも同様ですね 肩の追加装備 パーツ構成が複雑なので簡単に内訳を表記しておきました 肩としても手甲としても成立するように意識して構成してます 関節をうまく配置して装甲が移動するようにしているので、各ポジションでシルエットも意外と変わってます アグニレイジの爪部分なんかは、肩装備時はシリンダー基部のようにも見えますね 膝追加装備 通常時と攻撃時でかなり機体のシルエット変化に貢献してるパーツですね 膝そのものの可動とフレキシブルな関節でアクション時は「蹴り」を魅せるためにも貢献してます テール部 背面を印象深く仕上げるのは私の癖というか好みの話になるんですが、テールパーツはその中でも効果が高い部位ですね 末広がりのシルエットにもしやすく、ここのボリュームを増すと機体の低重心化にもひと役買ってくれます 延長部 全体のボリュームを増しつつスマートな印象も残すために数か所の延長工作をしています 足首は延長しつつブレードの固定具を兼ねた構成に 二の腕はシンプルにショートパイプを噛ませているだけです 首は少し手間をかけてプラバンで1mm長くしています この辺りの塩梅は結構デリケートで、やりすぎても変に長くなってしまうだけなので難しいところ 迷ったら、カッコいいと思ったロボットの手足のバランスを真似てみる、とかもアリですね 改めて組み上げた状態 蒼龍機 グランドラウザー! 手首はノーマルハンド・ネオを使用してアクションの幅を広げています 設定的にはグランドライザーの二番機を攻防一体の追加装備でグレードアップした、というイメージですね 翔龍機の名前の一部にもなっている龍の要素をもう少しわかりやすく前に出してみてます メタルグリーンの箇所は龍のウロコイメージ、膝ブレードは角度によって尻尾に見えたりします (露骨な尻尾を付けたくなかったということもありw) という事で三体目、ご紹介させていただきました 記事内で何度か「シルエット」というワードを使っていますが、 シルエットと色の印象で初めのインパクトは決まる といっても過言ではないので、もし何かの模型コンペに挑むことがあればこのことを思い出していただけると幸いです 最後に今回の作例三体をまとめて 全三回の作例紹介を通してグランドライザーの魅力が伝わったのではないかと思います 汎用性の高いデザインに仕上げたこともあって同じグランドライザーをベースとしていてもかなり印象の違う作品が作れますし、モデラー一人一人の個性を表現するのに向いている題材なのではないかとも思いますね 購入を迷っているそこのあなた!まだ予約受付中ですよ! それではまたどこかでお会いしましょう! sera ということで、翔龍機 グランドライザーのデザイン・原型のseraさんによる作例製作ブログを3連続でお送りいたしました。 購入後の製作の際のインスピレーションの一助になれば幸いです。 ぜひご予約もお忘れなく!

-
フォルムアームズ「翔龍機 グランドライザー」作例紹介第二弾
こんにちは、seraです 前回に引き続きグランドライザーの作例制作、第二弾となります! 今回は予告通り「フレームアームズとの融合」というテーマで作例をご紹介していきます ◆作例2:グランドライザー・アームズシフト はい。一見ミスマッチともとれる「レヴァナントアイ・イーギル」を使って、グランドライザーをミリタリー調に仕上げるという方針で仕上げています しかし見ていただけるとわかるようにミスマッチどころか初めからこういう機体であったかのように違和感なくまとまっていますね 各部を分解すると、手脚はほぼレヴァナントアイ・イーギルそのままであることがわかりやすいかと思います 足首はグランドライザーのものを使うために「メカサプライ06 ジョイントセットB」のボールジョイントを使用しています アーキテクトにレイルヴァースやグランドライザーの足首を使用するときは、基本的にこの方法が使えますので、お手元に届いた際にはぜひお試しください 肩の接続は無改造でも可能ですが「メカサプライ11 ジョイントセットC」の長めのプラキャップを使用すると保持が安定します 側面の軸は飛び出さない長さまで切り取っています バックパックは側面の3mm穴を活用 「ウェポンユニット03 フォールディングキャノン」と「ウェポンユニット36 ミサイル&レドーム」を取り付けています ミサイルのアーム基部は軸を片方カットした「メカサプライ11 ジョイントセットC」を使用しています グランドライザー商品ページの写真だと「ウェポンユニット51 カスタマイズブレードセット01」を懸架していたりしますが、こういう仕上げだとアームを介して背部武器を装備させるのも面白いですね 手持ち武装の「ウェポンユニット49 ストライドSMG」と「ウェポンユニット50 コンポジットプレートユニット01」の付属ナイフ こちらは試作品をいただいていたので折角なので使わせてもらいました 余談ですがストライドSMGのグレネードは「プラユニット P145 ショートパイプ」の2mmを使うと弾が装填されている感が増すのでおススメです それでは改めて組み上げた状態 グランドライザー・アームズシフト! 初めにも書きましたが、今回は一見してミスマッチなものを混ぜるという方針でグランドライザーにレヴァナントアイを混ぜるというミキシングをしています ただ、ミキシングと言いつつ実態はフォルムアームズの手脚を既存フレームアームズのものに置き換えるというシンプルなもの 試作段階で轟雷やヴァイスハイトの手脚なども置き換えてみましたが、色を合わせるだけでも驚くほど馴染むので是非試していただきたいですね 手首はグランドライザーに付属の物、基本的にはFAハンドの武器持ち手と同じなので使用感もほぼ変わりないです パーツ数が少なくなっていますが実用に何の支障もないことをお伝えする意味でも今回はこれを使いました 今回唯一のミキシング武器、左肩に装備させてる「ウェポンユニット43 エクスキャノン」に「メカサプライ07 エクスアーマーA」のプレートを貼っただけの簡易的なミサイルが結構気に入っています という事で二体目、ご紹介させていただきました ふつふつとミキシング欲が湧いてきたのではないでしょうか? 次回!フォルムアームズ第三段階のカスタム、「自分の中のカッコいいを追求する!」をお楽しみに! sera

-
フォルムアームズ「翔龍機 グランドライザー」作例紹介第一弾
フォルムアームズ第二弾「 翔龍機 グランドライザー 」絶賛ご予約受付中です! 塗装完成見本は来週にはお見せできるかと思います。もう少々お待ちください。 本日はそのグランドライザーの遊び方提案として、作例ブログをお届けいたします。 フレームアームズもそうですが、商品性質上やはり組み換えや改造の作例をご紹介するのが遊びのイメージを膨らませやすいのではないかと思ったのですが、誰がやるのか? 組み換えがうまい人・・・ あれ?そもそもseraさんはコトコン2016のフレームアームズ部門で 金賞 を取るくらい組み換えがうまい人だぞ? ということでルミナスクイードまでの商品原型を終えたseraさんに作例制作をお願いしました。ここからは弊社ブログ初登場となるseraさんにご紹介いただきます。 こんにちは、はじめまして フォルムアームズ初期シリーズ、デザイナー兼原型のseraです 本日は2025年3月発売予定「翔龍機 グランドライザー」の作例制作という機会をいただきましたのでその紹介となります 今回は「翔龍機 グランドライザー」(以下グランドライザー)の改造例を難易度別に三段階に分け、三つの作例を紹介するという形で進めさせていただきますのでよろしくお願いします ◆作例1:グランドライザー武威カスタム グランドライザーはモチーフの中に鎧武者が含まれているのは既にご存知かもしれませんが、これはその要素をひときわ目立つようにカスタムしたものになります 使用パーツは主に「メカサプライ23 エクスアーマーF(ロボット用)」「メカサプライ24 エクスアーマーG(ガール用)」「武威登龍 “凱風快晴”」となっています 一体目は グランドライザーにM.S.Gやヘキサギアをシンプルに組み込む 、というコンセプトで 比較的再現性の高い(真似をしやすい)作例 になるように意識して構築しています 肩はエクスアーマーFのものをそのまま使用しており、下腕接続も無改造で可能です(関節の幅が気になる場合は側面に丸モールド系のM.S.Gを張り付けても良いかもしれません) ここはフォルムアームズのフレームアームズとの互換性を効果的に活かした箇所ですね 膝装甲もエクスアーマーFのものをそのまま使用しています。接続には「メカサプライ18 ジョイントセットD」と「ヘヴィウェポンユニット31 轟槍鬼十字」を使用していますがここは適当な関節で代用可能です グランドライザーは膝を外すと3mm軸が露出するのでこれを活かした箇所ですね 腰フロントアーマーは少し複雑な構成になっていますがエクスアーマーGを中心に武威登龍、「メカサプライ06 ジョイントセットB」、「メカサプライ11 ジョイントセットC」、「プラユニット P145 ショートパイプ」、そして先に外したグランドライザーの膝パーツで構成しています 腰サイドアーマーと腕部追加装甲 こちらは武威登龍の物をそのまま使用しています 腰はジョイントセットBのボールジョイントを使用してますが、こうしておくと干渉を避けて取り付けやすいですね バックパック 武威登龍の肩アーマーからフロントアーマーに使用したパーツを抜いた状態 形状を安定させるために「ヘキサギア EXユニット001」を使用しています かなりの重量物なので関節を強化するか、いっそ外してしまって遊びやすさを重視するのもアリですね 改めて組上げた状態 グランドライザー武威カスタム! ハンドパーツは武威登龍の物を使用。少し腕部が長くなりますが全体的にゴツいシルエットに変わっているので違和感は少ないかと思います 刀は武威登龍そのままですがグランドライザーの余った肩パーツで装飾しています 元々細マッチョのイメージでデザインしたグランドライザーですが、こうして装飾すると鎧を着こんだ屈強な戦国武将としても成立させることができますね 今回の構成では切った貼ったなどの不可逆な改造は一切なく、気軽な組み換え遊びとして成立するので、お手元に届いた際にはぜひとも試していただきたいところですね ちなみにこれだけ装甲を追加してもさほど可動範囲の低下はないので安心してブンドドを楽しんでください! という事でまずは一体目、ご紹介させていただきました 次回!フォルムアームズ第二段階のカスタム、「フレームアームズとの融合」に踏み込んでいきます! sera

-
フレームアームズ「バーゼラルド・ゼルフィカール フルオプションセット」サンプル紹介
2024年10/25(金)コトブキヤショップ各店にて販売開始です。パッケージ他サンプルを軽くご紹介します。

-
フォルムアームズ第二弾「翔龍機 グランドライザー」テストショットご紹介
最初のテストショットにて商品状態イメージのご紹介になります。

-
フォルムアームズ新デザイナー参戦!
続報はしばらく先になりますが、こうご期待!!


フレームアームズ・フォルムアームズ公式ブログ
すべて
(20件中、1~10)